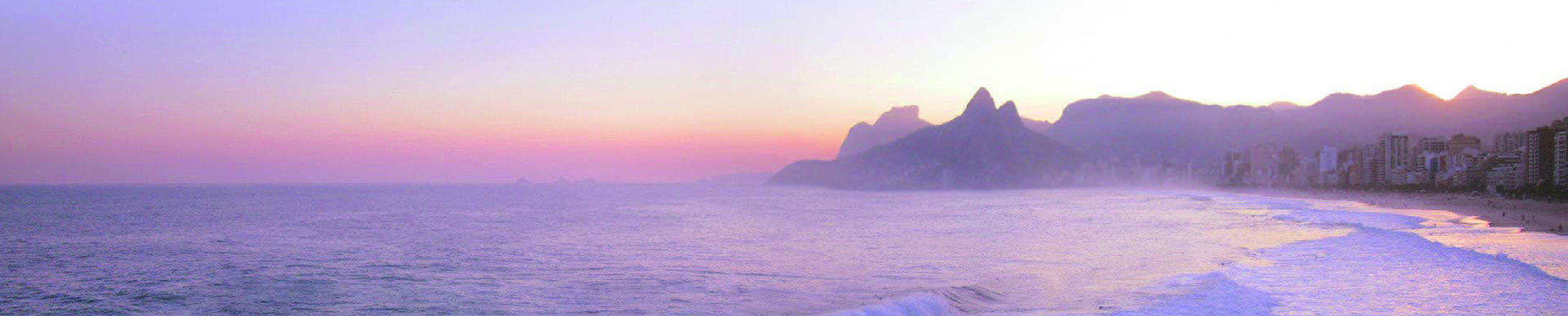<序>
David P. Appleby(以下アプレビー)をはじめとした従来のヴィラ=ロボス研究においてもしばしば指摘されているように、ヴィラ=ロボスの作品を通時的に整理したとき、1920年代(とりわけ1923年から1930年)が一つの区切りとなる。この期間において、ヴィラ=ロボスの作風は大きく変化を遂げ、「ブラジル性」が作品に色濃く反映されるようになるのである。1923年から1930年という期間にヴィラ=ロボスに訪れたもの、それはヨーロッパとの邂逅であり、「パリ体験」であった。
しかし、このように作風を変化させる契機となったパリ滞在中、ヴィラ=ロボスがどのように過ごしていたかということは、日本で十分に紹介されているとはいえない。一方でまた、数多くの研究が成されている1920年代パリをめぐる音楽史のなかでも、ヴィラ=ロボスの位置づけというのは僅かな議論に留まっていることが多い。そこで拙稿では、1920年代パリの音楽文化状況を整理しながら、アプレビーらの先行研究をもとに、この「狂乱の時代 Les Années Folles」におけるヴィラ=ロボスのパリ体験を追うことで、ヴィラ=ロボスの作風が変化していく過程を描いてみたい。
ヴィラ=ロボスのパリ体験を伝記的に追いつつ、1920年代のパリの文化的諸相の中に置き直してみること。それによって、ヴィラ=ロボスの「ブラジル的な」作品を形成せしめた社会・文化的要素を浮き彫りにすること。そして、1920年代のパリに滞在した経験が、1930年以降に書かれて行く一連の『ブラジル風バッハ』の制作に影響を与えている可能性を指摘し、『ブラジル風バッハ』の位置づけを再考することを目指す。なお、Bachianas Brasileirasの訳語としては、『ブラジル風バッハ』は必ずしも適切ではないが、日本においては慣例上このように訳されることが多い事を鑑みて、本論ではさしあたり『ブラジル風バッハ』の訳を用いる。
<ヴィラ=ロボスのパリ体験>
まずはじめに、ヴィラ=ロボスのパリ体験を整理しておこう。
1923年7月-24年9月 第一次パリ滞在
1924年9月-26年12月 ブラジル帰国
1926年12月-1929年8月 第二次パリ滞在
1929年8月-1929年9月 ブラジル帰国
1929年9月-1930年 第三次パリ滞在
ヴィラ=ロボスは1922 年の「モダン芸術週間 Semana de Arte Moderna」に参加した後、1923 年にブラジル政府から援助金を獲得し、フランスに渡った。これがヴィラ=ロボスにとってはじめてのヨーロッパ体験であり、これ以降、二度の帰国を挟みながらも、七年間にわたってパリを拠点として音楽活動を展開していくことになる。そしてまさに、第一次パリ滞在から帰国直後の1924 年から1930 年の間に、ヴィラ=ロボスの代表作である14 曲の『ショーロス』の多くが作曲されることになる。青年期にブラジル国内を旅していたヴィラ=ロボスは幼い頃より「ショーロ」(リオを中心として展開されたブラジルのポピュラー音楽の一ジャンルで、即興が重視される)に親しんでいたが、この『ショーロス』を本格的に書き始めるのがパリ滞在を経てからであるという点は、本論において重要な意味を持っている。そしてまた、パリから帰国したのちの1930 年から1945 年の間に、 もう一つの代表作である「ブラジル風バッハ」が書かれることになることも見逃すことはできない。
<1923年-24年 第一次パリ滞在>
リオデジャネイロを発ってはじめてパリに向かうヴィラ=ロボスは、パリにおける自身の成功を確信していた。リオデジャネイロにおける「アヴァン・ギャルド」として、また、ドビュッシー以来の革新を引き継ぐ作曲家としての自負を持っていたという。彼がパリについた直後になされたインタビューによれば、「私はここに勉強にきたのではない。自らが既に達成したものを見せるために来たのである。」と豪語している。そしてまた、アプレビーが指摘するように、
「1920年代には、ブラジルの芸術家や音楽家たちは、自分たちのことをブラジルとフランスという二つの国家の市民であると想像していた。
Appleby, David P. Heitor Villa-Lobos, A Life(1887-1959), p.65
のであって、ヴィラ=ロボスも例外ではなかった。しかし当然のことながら、パリに到着したときのヴィラ=ロボスは、マネージャーがいたわけでもなければ、コンサートの予定もなかったし、ヴィラ=ロボスのことを知っているフランス人もほとんどいなかった。それに加えて、パリについてからしばらくのちに招かれた、画家タルシラ・ド・アマラウのアトリエにおける昼食会で、エリック・サティとジャン・コクトーに出会ったことが、彼の自負を打ち砕くことになった。この昼食会でヴィラ=ロボスはコクトーのまえで即興を弾いてみせることになるのだが、それに接したコクトーの感想としては、「ドビュッシーやラヴェルのスタイルの物真似以上のなにものでもない」という辛辣なものであった。これに対してヴィラ=ロボスは激怒し、コクトーとほとんど殴り合う寸前までいったという。
ヴィラ=ロボスが自身の才能にどれほど自負を持っていても、パリで作曲家として大成するうえで、ジャン・コクトーに認められないのは致命的であった。というのも、当時のコクトーは、ディアギレフやストラヴィンスキー、サティやピカソ、さらにはオーリック、ルイ・デュレー、オネゲル、タイユフェール、ミヨー、プーランクらいわゆる「六人組」など、この時代のパリに集った芸術家たちの交流における中心的立場を占めていたと同時に、
«Je demande une musique française de France »(「私はフランスのフランス音楽を求める」)
と自ら語っていたように、フランス音楽を保護するものとしての立場を鮮明にしていた。さらにまた、「19世紀の首都」(ベンヤミン)であったパリは、20世紀初頭の「ベル・エポック」あるいは「祝宴の時代」(ロジャー・シャタック)と呼ばれた時期においても、数々の芸術運動や先鋭的な上演の成される街であり続けていた。
1912年5月29日には、シャトレ座でニジンスキー『牧神の午後』が初演され、
「上演中、観客は静まりかえっていたが終わったとたん、熱狂的な喝采と、ブーイングと、野次と怒号が同時に沸き起こる」
シェング・スヘイエン『ディアギレフ 芸術に捧げた生涯』(鈴木晶訳、みすず書房、2012)p.243
という反応であったし、翌年1913年の同日5月29日には、シャンゼリゼ劇場で『春の祭典』が初演されて大スキャンダルを巻き起こしていた。1914年以降の第一次世界大戦を経ても、
「戦争が終わる前から、サティやさまざまな若いパリッ子たちは世紀末のしかつめらしさを拒否し、ミュージック・ホールの音楽やラグタイム・ジャズを利用した。またノイズをつくりだすダダの精神にも賛同した。」
アレックス・ロス『20世紀を語る音楽 1』(柿沼敏江監訳、みすず書房、2013)p.81
という様相であり、20年代に入っても
「1920年代のヨーロッパ。そこでは、非西欧地域の異質の文化を積極的にとりいれながら、活気のある、自由な、開かれた感受性がくりひろげられようとした時代だった。1920年代のヨーロッパ音楽のひとつの特徴も、まさにこのことだった。ジャズやタンゴといった異文化の音楽、その未知の感受性をとりこんで、新精神(エスプリ・ヌーヴォー)の生き生きとした音楽を生み出していこうとしたのである」
「こうして、ジャズはあっという間にヨーロッパ中に伝染していった。”六人組”の作曲家たちにみられた1920年代のモダニズム。それはこのようにジャズの影響が異種交配されてかたちづくられていったのものだったのである。」
秋山邦晴『エリック・サティ覚え書』(青土社、2016)p.198
というように、次々と新しいスタイルが取り入れられていく実験的な場であり続けた。ヴィラ=ロボスがはじめて訪れたころのパリというのは、こうした人物や経験を抱え込んだパリであり、まさしく『狂乱の時代 Les Années Folles』の只中にあるパリであった。『春の祭典』初演の衝撃から10年が経ち、ジャズがカジノ・ド・パリに初めて登場してから5年が経過していた。ダダイスムとシュルレアリスムが闘争を繰り広げ、シェーンベルクが12音技法を試み、オネゲルが『パシフィック231』を完成させ、デュシャンが「大ガラス」を作成した年であった。
こうしたパリの状況に身を置いたヴィラ=ロボスは、コクトーとの争いからしばらくのち、自分の現在の作品では、さらなる新しさを求めるフランスの聴衆を惹きつける上で不足していることを自覚しはじめる。一方で、金銭的な支援を得るためにポリニャック夫人のサロンに近付きながら、ブラジル滞在中に出会ったピアニストのアルトゥール・ルービンシュタインのサポートを得て、自身の作品の演奏機会を作っていくのである。
1923年10月23日、パリではじめて、彼の作品が演奏された。曲目は『ヴァイオリンとピアノのための幻想的ソナタ一番』『ピアノのための無言歌』『ソプラノとヴァイオリンのための乙女と歌』という三曲であり、いずれも編成・タイトル・内容ともに、後年のヴィラ=ロボスの作品にあるような「ブラジル的な」独自性を感じさせるものではなかった。ついで1924年2月14日に『赤ちゃんの家族 第二集』(A prole do bebê no.2)4月4日に『ピアノトリオ第三番』が演奏されることになるのだが、アプレビーも指摘するように、ヴィラ=ロボスの最初のヨーロッパ滞在中のもっとも重要なコンサートは、1924年の5月30日夜9時からSalle des Agriculteursで行われたコンサートであろう。
このコンサートではアルトゥール=ルービンシュタインが『赤ちゃんの家族 第一集』(A Prole do bebê no.1)を弾き、また、『ノネット ブラジルの簡潔な印象』(Nonetto:Impressão rápida de todo o Brasil)が初演されて大きな注目を浴びた。確かにこの『ノネット』はフルート、オーボエ、クラリネット、サックス、ファゴット、ハープ、チェレスタ、打楽器に加えて、混声合唱が組み合わされた編成という点でも斬新であった。大量の打楽器の利用を用いた強烈なリズムに貫かれており、そのなかに、歌詞というよりはリズムを補強する側面の強いプリミティブな合唱は、当時のパリにおいてもほとんど聞かれたことのないものであっただろう。さらにまた、これはパリで演奏されたヴィラ=ロボスの作品としてはじめて、タイトルに「ブラジル」を用いた作品でもあった。
1924年8月11日、ヴィラ=ロボスはヨーロッパ滞在を延長するために、自身のパトロンのアーノールド・グインレにさらなる支援を要求するが、グインレのアドバイスから、ブラジルに一時帰国して資金調達を行うことでヨーロッパ滞在延長を狙うことへと方針を転換する。Max Eschig社から自身の作品の楽譜の出版契約をしたのもこの時期であった。
<1925年の一時帰国と『ショーロス』>
1925年2月18日、サンパウロのTheatro Sant’ Annaで、コンサートを開催する。前年にパリで好評を博した『ノネット』を含むプログラムであり、このコンサートがOlívia Guedes Penteado と Dr.Paulo Pradoという彼の二人のパトロンに捧げられていることからも、パリにおける自身の成功を示して、ブラジル国内でさらなる資金調達に繋げることを狙っていたことを読み取ることが出来るだろう。ついで1925年9月17日には、ヴィラ=ロボスの作品を集めた室内楽コンサートがリオデジャネイロ国立音楽学校で開催され、好評を博す。しかし、このブラジル一時帰国中における活動としてコンサート以上に注目すべきは、後に彼の代表作となる『ショーロス』の多くがこの期間に作曲あるいは構想されていることである。ヴィラ=ロボスの作品一覧を概観したとき、1925年前後に完成された作品というのは、ほとんどがこの『ショーロス』であり、他にはピアノ曲『シランディーニャス』(Cirandinhas)が挙げられるぐらいであろう。
若い頃から親しんだブラジルの民族音楽「ショーロ」を一連の『ショーロス』として昇華させ、作品の形に結実させるために、故郷を相対化する機会としての異国体験を必要としただけではない。ジョルジェ・コリが指摘するように、「1922年以前の作品は圧倒的に、議論の余地もなくフランス的である」のだが、『狂乱の時代』のパリにしばらく身を置いた結果として、自身がパリで作曲家として生きていくためには、ブラジル的な要素を用いたエキゾチックでセンセーションな曲想が必要とされていることを認識し、「ブラジルの野性」(le sauvage brésilien)を求めるパリの聴衆の希望に応える形で、自身の作風を戦略的に変化させていったのである。
「ヴィラ=ロボスは、その天才性からだけでなく、「南国の」作曲家としての地位を確保するために、ヨーロッパでブラジル風の音楽を書いたのである。」
ジョルジェ・コリ「近代的で民族的なエイトール・ヴィラ=ロボス」
ブラジル外務省文化部編『ブラジリアン・クラシック・ミュージック』所収、 P.76
<1926年12月、第二次パリ滞在以降>
パトロンのグインレからの資金援助を受け、このブラジル滞在期間に書き上げた『ショーロス』を携えて、ヴィラ=ロボスはふたたびパリに戻った。今度は妻・ルシリアを伴っての渡航であった。第二次パリ滞在中のヴィラ=ロボスは、1927年3月2日、「私は困惑の極みにあり、経済破綻に怯えています。」とグインレにさらなる資金援助を要請することになるのだが、ヴィラ=ロボスが資金援助によって達成しようする目標は、Max Eschig社から自身の作品の楽譜を出版するための費用を捻出することにあった。というのも、この時期のヨーロッパにおいて、作曲家としての名声を確立するための方法は、第一にコンサートで自作を上演して批評家から好評を得ることであり、第二に作品の楽譜を出版して、演奏家にとって作品をアクセス可能にすることであったからだ。パトロンであったグインレは、ヴィラ=ロボスのこの要求を許し、結果としてMax Eschig社から彼の15作品が年内に一挙出版されることになるのである。
1927年10月24日と12月5日には、パリのメゾン・ガヴォーのコンサートホールで、「ヴィラ=ロボスの作品に捧げられたフェスティヴァル」(Festivals, consacrees aux oeurveurs de Heitor Villa-Lobos.)が開かれるに至った。10月にはショーロス2番、ショーロス4番、ショーロス7番、ショーロス8番、12月にはこれに加えてショーロス3番、ショーロス10番が演奏された。ルービンシュタインの記録によれば、このコンサートにはプロコフィエフやラヴェルも同席していたという。
この『ショーロス』をメインとしたコンサートに対して、パリの批評家たちは惜しみない賞賛を贈った。たとえばフローラン・シュミットはLa Revue de Franceにおいて、「この並外れたブラジルの音楽家は、いま、私たちを圧倒した」と絶讃し、アンリ・プルニエールはLa Revue Musicalにおいて、この二つのコンサートが
«C’est la première fois qu’en Europe on entend des oeuvres venues de l’Amérique latine et qui apportent avec elles les enchantements des forêts vierges, des grandes plaines, d’une nature exubérante, prodigue en fruits, en fleurs, en oiseaux éclatants.»
「それはヨーロッパにとって、ラテンアメリカからやってきた作品をはじめて聞いたときであった。原生林や巨大な植物、生い茂る植物に豊富な果実、花々、そしてさえずる鳥たちといった熱帯の魅力が、ヨーロッパにはじめてもたらされたのだ。」
PRUNIÈRES, Henri, Revue Musicale, janvier 1928.
として、その感動がプリミティブなものの集大成であったことや、全くもって新しい経験であったことを描いている。「ドビュッシー風の」などという派閥を継ぐ形ではなく、「はじめて première fois」と形容されること – これはヴィラ=ロボスにとって、狙っていた通りの反応であっただろう。なぜならばヴィラ=ロボスは、ブラジルあるいはフランスのどの「モダニズム」にも属そうとはせず、独自の作風を打ち出すことを目指していたからだ。1920年代パリの聴衆の希望に応える形で自らの作風を変容させながら、しかし派閥に頼ることなく評価を確立していったということがヴィラ=ロボスの特徴であった。
しかし、アプレビーが指摘する様に、パリの聴衆が求めるようなエキゾチックな音楽を作れば作るほど、ヴィラ=ロボスは板挟みの状態に陥っていったようだ。エキゾチズムを増せば増すほどブラジル=野性(sauvage)/パリ=文明(civilization)というイメージを強めていくことになり、結果として、ブラジル人たちからの反発を買うことになった。そのような状況を抱えつつ、1929年の8月から9月にかけて、ヴィラ=ロボスはブラジルへ帰国してリオデジャネイロとサンパウロで彼の作品のコンサートを指揮し、ブラジルでの評価を高めるが、すぐにまたパリに戻る。そして、1930年5月のパリでのコンサートを区切りに、以後は拠点をブラジルに戻すことになるのである。
<『ブラジル風バッハ』の成立>
パリからの帰国後、すなわち1930年以降、ヴィラ=ロボスの代表作である一連の『ブラジル風バッハ』が作曲されていく。ヴィラ=ロボスのバッハへの傾倒については、1921年の時点ですでに、J.S.バッハの『平均律クラヴィーア曲集 第二巻』の「フーガ第21番」を8台チェロ用に編曲していることが知られており、またヴィラ=ロボス自身、1945年の手紙の中で「芸術の世界において、最も聖なる贈り物であることは疑うべくもない」とバッハの音楽の特別性を表明している。しかし、バッハへの傾倒や、バロック音楽とブラジルのポピュラーミュージックの即興に同じ要素を見出したというヴィラ=ロボス本人の言説が残されているゆえに、なぜ「1930年」というこの時期に、彼のアイデアがBachianas Brasileirasというタイトルのもとで結実したかということについては、十分な考察が成されてこなかった。
まずは1920年代の音楽状況として、たとえばストラヴィンスキーが『プルチネルラ』組曲で展開していったように、新古典主義の潮流が生まれていたことにも目配りする必要があるだろう。新古典主義の特徴は、ロマン主義以前の様式、とくに秩序をもった様式的なバロック音楽を現代的な手法で洗練・発展させることにあるが、その意味においては、ヴィラ=ロボスのバッハへの回帰というのは、ある種の新古典的主義への転回だと位置づけることも可能だからだ。しかし、そうであるとするならば、ヴィラ=ロボスは1930年よりも早い段階で新古典主義の作風へ移行することもできたはずであり、1930年以降になってはじめて、この一連の作品が生み出される理由としては、不十分であると言わざるを得ない。そこで、1926年から1930年にかけてヴィラ=ロボスが遂げた作風の変容と、それゆえに陥った先述の「板挟み状態」を鑑みて、ひとつの仮説を提示しておきたい。
Bachianas Brasileirasとは、1920年代後半のパリにおいてヴィラ=ロボスが経験した「板挟み状態」に対する打開策として編み出された作品だったのではないだろうか。先述したように、エキゾチズムを増せば増すほど「野性」と「文明」のコントラストが際立ってしまうという板挟み状態から脱し、それでいて、西洋の聴衆が求めていたエキゾチズムやプリミティブな要素を自身の作品のなかで確保するためには、両者を融合させた作品を書く必要があったのではないか。
当時のブラジルをめぐる政治状況とヴィラ=ロボスの政治的立場を考慮すると、この仮説はさらに補強されることになる。ブラジルでは、1920 年代にナショナル・アイデンティティを求める動きが高まっており、1930 年のヴァルガス革命以降はナショナル・アイデンティティ(すなわちBrasilidade)の獲得が国家レベルで推進されていた。ナショナル・アイデンティティ獲得の一環として、西洋に通用する「ブラジルを代表する作曲家」の存在が切望される社会的背景があったのである。1930 年にフランスから帰国したヴィラ=ロボスは、すぐに教育庁の文化顧問に就任することになるのだが、その立場ゆえ、パリ滞在中のようにブラジル的なものを「エキゾチック」な要素として作品に取り込むのではなく、西洋的要素と並びえるものとして取り入れて自らの音楽表現を確立していくことを自他ともに要求されることになったのではないだろうか。
プリミティブでエキゾチックな要素を、あらゆる派閥や音楽の源流にあるような「バッハ」と組み合わせること。Bachianas Brasileiras、正確に訳すならば「バッハ風・ブラジル風の音楽」「バッハ風のブラジル音楽」となるように、少なくとも表題のうえでは、この二つはほとんど対等なものとして扱われていることに注意したい。 こうした発想は、タイトルのBachianas Brasileirasという表記のみならず、九曲あるBachianas Brasileirasの各楽章の表題を参照しても読み取ることができる。以下にBachianas Brasileiras全9曲の内訳と作曲年代、編成を掲げる。
第一番(1930 年作曲、チェロ八重奏)
第一楽章:序奏/エンボラーダ
第二楽章:プレリュード/モヂーニャ
第三楽章:フーガ/コンヴェルサ第二番(1930 年作曲、民族楽器を用いた一管編成オーケストラを想定)
第一楽章:プレリュード/カパドシオ(ペテン師)の歌
第二楽章:アリア/われらが大地の歌
第三楽章:舞曲/奥地の思い出
第四楽章:トッカータ/カイピラの小さな汽車第三番(1934 年作曲、ピアノと管弦楽のための協奏曲的作品)
第一楽章:前奏曲/ポンテイオ
第二楽章:幻想曲/脱線
第三楽章:アリア/モヂーニャ
第四楽章:トッカータ/ピカプ
第四番(1930 年から1941 年の間に作曲、ピアノ曲、1942 年に管弦楽化)
第一楽章:プレリュード/序奏
第二楽章:コラール/セルタン(ブラジル奥地の歌)
第三楽章:アリア/カンティガ(歌、古謡)
第四楽章:舞曲/ミウヂーニョ(黒人に伝わる小刻みな足踊り)第五番(1938 年作曲、1945 年改訂、チェロ八本とソプラノのための作品)
第一楽章:アリア/カンティレーナ
第二楽章:踊り/マルテロ第六番(1938 年作曲、フルートとファゴットのデュオ)
第一楽章:アリア/ショーロ
第二楽章:幻想曲第七番(1942 年作曲、管弦楽曲)
第一楽章:前奏曲/ポンテイオ
第二楽章:ジグ/カイピラ風カドリーユ
第三楽章:トッカータ/一騎打ち
第四楽章:フーガ/対話第八番(1944 年作曲、管弦楽曲)
第一楽章:前奏曲
第二楽章:アリア/モヂーニャ
第三楽章:トッカータ/カティーラ・バティーダ
第四楽章:フーガ第九番(1945 年作曲、合唱曲・弦楽合奏曲)
第一楽章:前奏曲/ゆっくりと神秘的に
第二楽章:フーガ/少しテンポを上げて
このように、九曲からなる「ブラジル風バッハ」あるいは「バッハ風ブラジル音楽」は、そのタイトルに「ブラジル」を冠するのみならず、ほとんどの楽章において、西洋音楽の楽章にわれる様式表現と共にブラジル的な副題が併置されているという特徴を持つ。しかし、第九番のみ、どの楽章においてもブラジル的副題が付されていないことに注目する必要がある。(部分的に副題が示されていないのが第六番と第八番である。第六番二楽章は「幻想曲」のみで副題が示されていないが、これは幻想曲Fantasia という題がブラジル的要素も含んでいるという点で併記することを避けたのか、あるいは第一楽章に示された副題「ショーロ」が継続している可能性が考えられる。第八番については、第一楽章「前奏曲」と第四楽章「フーガ」のみに副題が示されていないが、第九番の「前奏曲」「フーガ」へと繋がる思考をここに見出すことが出来るだろう。)
おそらくそれは、ブラジル的要素を失ったものとしたのではなく、ブラジル的要素と西洋音楽の要素が完全に一体化したことを示すものではないだろうか。カンドンブレ(ブラジルの民俗信仰)の儀式の音楽を思わせる荒々しく執拗なリズムが流れ続ける一番の第一楽章から始まったブラジル風バッハは、九番に至って「バッハ風」と「ブラジル音楽」の完全なる融合を果たすのである。
とりわけ第九番第二楽章の八分の十一拍子のフーガは、五拍子(=ブラジル音楽に特徴的なリズム)+六拍子(=西洋音楽の源泉となるリズム。12世紀末のノートルダム楽派の当初は、三位一体説を反映して、八分の六拍子が主要であった。)の組み合わせであり、ブラジル的な音楽と西洋的な音楽が拍子のうえでも緊密に結びつけられている。
そしてまた「九番」においてブラジル風バッハを完結させたことには、西洋の偉大なる作曲家として九つの交響曲を書いたベートーヴェン、シューベルト、ドヴォルザーク、マーラー(それぞれ九つの交響曲を書いている)らと並ぶブラジル音楽の金字塔をその作曲生涯において打ち立てようとしたという意図を読み取ることが出来る。九番が当初合唱曲として構想されていたこと(ベートーヴェンの第九番『合唱つき』を想起させる)、ブラジル風バッハ第九番フーガの最後の和音が、Cの音一種類に集中することも、この九番をもって連作の到達点とする構想が当初からあったことを裏付けるだろう。(なお、ヴィラ=ロボスは1959 年まで存命であったから、ブラジル風バッハ九番を完成させた1945 年以後もブラジル風バッハを書く時間的余裕はあったと考えられる。)
<『ショーロス』から『ブラジル風バッハ』へ>
以上、1920年代のヴィラ=ロボスのパリ体験を追いながら、『ショーロス』から『ブラジル風バッハ』にいたる作風の変遷を生み出した様々な要因を考察してきた。『ショーロス』の成立はパリ体験に大きく影響されていることと、ブラジル性を強めて行くヴィラ=ロボスの作風の変化が、作曲家本人の芸術的思考の変遷はもちろんのことながら、社会的状況に大きく影響されていることを示そうと試みた。
端的に纏めれば、ヴィラ=ロボスの作品に「ブラジル性」が強まっていくのは、パリ体験という出来事を経てからであり、その結実が『ショーロス』であった。ヴィラ=ロボスが幼少期から接してきたブラジルの民族音楽を「ブラジル性」として昇華するためには、海外へ渡ることによって自らを相対化する機会を持たなければならなかったし、パリの聴衆にあわせて作風を変化させたという側面を見過ごしてはならない。しかし、このようにブラジル性を強めて行く作風の変遷が、ある種の板挟み状態を生むことになり、打開策として『ブラジル風バッハ』が生み出されることになった。その意味においては、『ブラジル風バッハ』もまた、ヴィラ=ロボスの1920年代のパリ体験が生み出した楽曲であったといえるだろう。とはいえ、この小エッセイでは『ブラジル風バッハ』の成立をめぐって仮説を提言するに留まったにすぎない。1930年以降のヴィラ=ロボスの動向、および『ブラジル風バッハ』をめぐる詳細な分析については、また稿を改めて議論することとしたい。
日本ヴィラ=ロボス協会会長・指揮者 木許裕介
(風間書房『明日へ翔ぶ4 人文科学の新視点』所収論考のリバイズ、2017年)