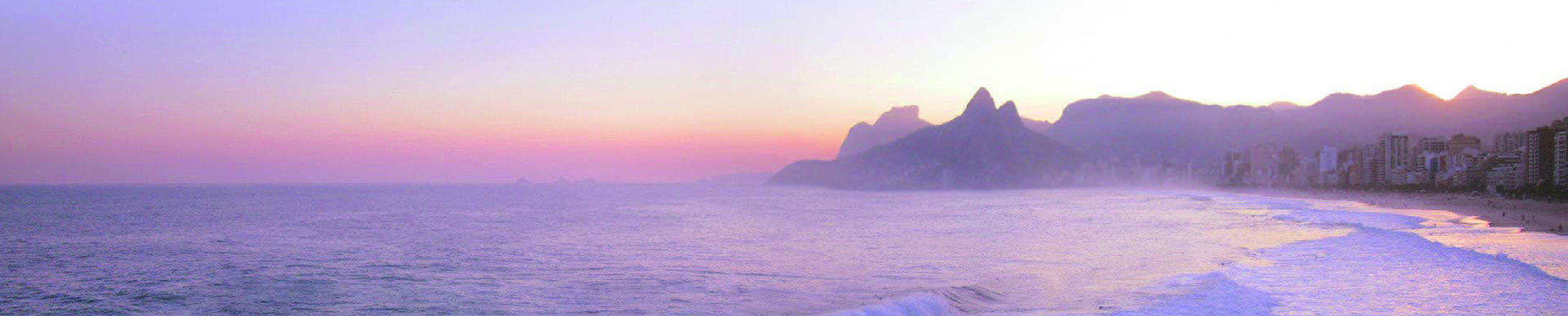Program
“O fascínio da música clássica brasileira”
Dialogue between Maestro Emmanuele Baldini and Maestro Yusuke Kimoto
ブラジル・クラシック音楽の魅力に迫る! – エマヌエーレ・バルディーニと木許裕介による対談
Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
Violin Sonata (Sonata Fantasia)No.2 (1914)
ヴァイオリン・ソナタ(ソナタ・ファンタジア)第2番
1st mov : Allegro non troppo アレグロ・ノン・トロッポ
2nd mov : Largo ラルゴ
3rd mov : Rondo Allegro Final ロンド、アレグロ・フィナル
Camargo Guarnieri(1907-1993)
Encantamento 魅了するもの(1941)
ヴァイオリン:エマヌエーレ・バルディーニ
ピアノ:清水安紀
於:代官山ヒルサイドバンケット
Profile

エマヌエーレ・バルディーニ /Emmanuele Baldini
ヴァイオリニスト、指揮者。サンパウロ州立交響楽団コンサートマスター、サンパウロ州立タトゥイ音楽院弦楽オーケストラとスフェーラ・ムンジオーケストラの常任指揮者を務める。 ソリスト、またはヴァイオリンとピアノによるリサイタルでイタリア全土、ヨーロッパの主要都市、南米主要国の首都の他、アメリカ合衆国、トルコ、オーストラリア、中国、日 本を訪れ演奏を行う。
指揮をイサーク・カラブチェフスキー、フランク・シップウェイに師事した後、ほどなくして南米の著名なオーケストラを指揮し始める。また、2017年から2020年までチリのヴァルジヴィア室内楽団の音楽監督を務めた。
これまでにAgorà、Rivoalto、Phoenixより40枚以上のアルバムを発表。近年はブラジル音楽作品の認知度を上げるために精力的に取り組み、Biscoito Finoよりグアルニエリのソナタ、オズワルドの四重奏と五重奏、Naxosのコラボレーション にてミゲスのソナタ、ベラスケス、ヴィラ=ロボス、サントロ、ミニョーネの作品を録音した。
次の発表は、これまで殆ど演奏されてこなかったフランシスコ・ミニョーネのヴァイオリン協奏曲(ジャンカルロ・ゲレロ指揮、サンパウロ州立交響楽団と共演)、イタリアのソナタ集、アウメイダ・プラドに捧げる作品集を予定している。
過去にはボローニャ市立歌劇場管弦楽団、トリエステ管弦楽団、ガリシア交響楽団のコンサートマスターも務め、ミラノ・スカラ座管弦楽団とも共演した。2005年以降、サンパウロ州立交響楽団のコンサートマスターを務め、精力的にコンサート活動を行いながら若手音楽家のための後進の育成にも力を注いでいる。

木許裕介/Yusuke Kimoto
イタリアを中心に欧州で研鑽を積み、2018年、BMW国際指揮コンクール(ポルトガル)にて日本人初の第1位優勝。以降、国内のみならず世界各地のオーケストラや音楽祭から多数招聘され国際的な活動を繰り広げている。駐日ブラジル大使館と協働して日本とブラジルを音楽で繋ぐ企画を精力的にプロデュースしており、日本ヴィラ=ロボス協会会長として演奏・講演・執筆など多数。2022年には駐日ブラジル大使館と共に「ブラジル独立200周年記念コンサート」を企画・指揮。2023年には500ページの単著『ヴィラ=ロボス – ブラジルの大地に歌わせるために-』(春秋社)を上梓。Naxos Japanより発売の「Brasil em Concerto」シリーズの日本語盤解説もほぼ全てに渡って担当しており、ブラジルの作曲家を日本に紹介することに尽力。本シリーズのCD解説のみで執筆字数は10万字を優に超える。
国内では主要プロオーケストラと共演するほか、各地のジュニア、ユース、大学オーケストラの指導に顕著な実績を挙げており、2021年よりエル・システマジャパン音楽監督に就任。音楽を通した地域創生や、産学界と連携した音楽の場づくり・人づくりのプロジェクトなど革新的な活動でも注目を集めている。東京大学教養学部および東京大学大学院修了、修士(学術)。

清水安紀/Aki Shimizu
ピアノを田中星治、若尾輝子、平野邦夫、H,ブラウスの各氏に、室内楽をW,リネバー氏に師事。在学中よりソロ、室内楽、伴奏で国内外での数多くの演奏会に出演。またブラジル音楽の普及に注力し、ブラジル外務省主導プロジェクト「Brasil em Concerto」のローンチコンサートなどに出演する他、 CD解説執筆など幅広く活動する。武蔵野音楽大学器楽科卒業。日本ヴィラ=ロボス協会副会長、村方指揮法教室伴奏ピアニスト。
【エッセイ:ブラジル・クラシック音楽の魅力】
執筆:木許裕介
昨年9月、「ブラジル独立200周年記念コンサート」を企画してオール・ブラジルプログラムのコンサートを指揮し、11月にブラジルに渡って、500ページに及ぶヴィラ=ロボスの評伝を書いた。今年の夏には、群馬県の大泉町でProjeto Música Sem Fronteirasという団体とFellow Orchestraの合同演奏会を指揮してブラジルで最も有名なショーロ「Tico-Tico no fubá 」を一夜で三度も演奏して踊り倒し、11月には日本ブラジル中央協会と名古屋外国語大学でヴィラ=ロボスはじめブラジル・クラシック音楽について話し、今日ここでブラジルの誇るヴァイオリニスト、バルディーニ氏とご一緒する。その間、Naxos JapanのBrasil em concertoシリーズCDの日本語解説をたくさん書かせて頂いた。これら全てが約一年間で起こったことだ。
どうしてそんなにブラジル·クラシック音楽に打ち込んでいるのだろう?自分でもたまによく分からなくなる時がある。だけど、ブラジルのクラシック音楽には、私の何かをくすぐるものがある。楽譜を開いたときに、何にも考えなくても音楽が自分の身体にすっと入ってくるような、不思議な感覚。細かいことはいいんだよ、と語りかけてくるような大らかさ。高まり続けて天井を破ってしまうのではないかと思うぐらいの猛烈な勢い、心躍らずにはいられない独特のリズム。胸をきゅっと掴まれるような「サウダージ」に満ちた旋律に、眩いばかりの色彩。そうかと思うと、モノクロームの洗練された響きや、挑戦的な不協和音がビシバシと降ってくる。ヴィラ=ロボスの《ブラジル風バッハ》やアンドレ·メマーリの《バッハとの対話》みたいに、先行する作曲家の曲を曲中に引用することも堂々とやってみせるし、サンバやショーロの要素すら極めて自然に作品の中に入れ込んでくる。
この捉えどころのなさ。ジャンルの垣根をひょいと飛び越えてくる軽やかさ。汲めども汲み尽くせぬ無限の奥行き!ブラジル·クラシック音楽の魅力を一言で纏めることなんて出来ないし、むしろ決して纏めることができないこの不可解な多様さに惹かれているような気もするのだけど、それでも何か言うならば、作品の中に「異」が宿り、「異」を受け入れる風通しが常に確保されていることかなと思う。
作品の中に、異なるものが宿る。それはたとえば、ヴィラ=ロボスが「ファンタジア」という言葉で宣言しようとしたことにも通じよう。今日演奏される《ヴァイオリン·ソナタ第2番》は、正確には「ソナタ·ファンタジア」というタイトルになっていて、この「ファンタジア」という言葉は、ヴィラ=ロボスが形式の自由さを表すときによく用いた言葉なのだ。それは「西欧文化が作り上げた厳密なソナタ形式では書きませんよ」という抵抗の宣言であり、「定型化された形式に収まりきらない何かがあるし、それがあって良いのだ」という、異質なものの肯定だと読むことも出来るように思う。
ちなみにこの《ヴァイオリン·ソナタ第2番》は、初演当時のブラジルの音楽界にとっても相当に「異」なるものとして受け入れられたようだ。この曲は1914年の作曲、つまりヴィラ=ロボス27歳頃の作品。当時のヴィラ=ロボスは最初の妻であるピアニストのルシリアと結婚したばかりで、まだあまりピアノの奏法を知らなかった彼は、ルシリアからピアノについて教わる日々を過ごしていた。一方でリオデジャネイロにおいて彼は新米作曲家として次第に目立ち始めた頃でもあった。1915年11月13日、彼ははじめて、すべて自分の作品だけでプログラムされたコンサートを開くことになった。そのときに演奏された曲の一つがこの《ヴァイオリン·ソナタ第2番》だった。
本曲は3楽章から成り、演奏時間は20分程度。当時最も影響力ある批評家、オスカル·グァナバリーノはコンサートを聞いてこのように書き残している。
「(ヴィラ=ロボスの作品は)支離滅裂で、不協和音に満ちている。狂気に侵された音楽家たちがはじめて楽器を演奏するかのようにガラガラと音をたてる」
同時代においてヴィラ=ロボスの作品はそれほどまでに異質なものとして受け止められたのである。だが彼はむしろその批評を糧として、「アヴァンギャルドの作曲家」としての道を爆走して、1922年にサンパウロで開かれた「近代芸術週間」に出演するまでに至る。
これは当時のブラジルで最も先鋭的なアートプロジェクトで、ブラジルの文化芸術史上極めて重要なイベントである。画家·詩人·彫刻家·舞踏家など多分野のアーティストたちが参加し、ここにただ一人の作曲家として参加したのがヴィラ=ロボスであった。そしてこのイベント最終日の第一部最後の曲としてラインナップしたのが、またしてもこの《ヴァイオリン·ソナタ第2番》であったのだ。彼にとってこの曲は、当時の音楽シーンに対して「異」を突きつけるために重要なものであったに違いない。
せっかくヴィラ=ロボスのことを書いたので、少し続けてみよう。「近代芸術週間」で大成功を収めたのち、彼はパリに遊学する。「私はここ(パリ)に勉強に来たのではない。自らが既に達成したものを見せるために来たのだ」と豪語したという逸話が良く知られている。
しかしパリ到着後すぐに、最先端だと思っていた自身の音楽をジャン·コクトーに「ドビュッシーの二番煎じに過ぎない」と酷評されてから、ヴィラ=ロボスはさらに異なるものを探し求め始め、西洋の模倣ではない「ブラジルのクラシック音楽」をいかに創出するかということを強く試行し続けるようになった。たとえば《ショーロス》シリーズにおいて、ブラジルの人種·地域·歴史など様々な多様性を多様なままに統合し、ブラジル全土の印象を作品のなかに描き出すということに挑戦し、演奏がほぼ不可能なほど巨大な規模の作品を残した。
一方で、ブラジル的でありながらもヨーロッパで受け入れられる「普遍的な」音楽を志向し、音楽の原体験たるバッハにその活路を見出し、《ブラジル風バッハ》シリーズを編み出してみたり、ハイドンの研究に没頭してシンプルな弦楽四重奏曲を残したりもした。まさしく変幻自在と言ってもいいほど、その作風をわずか数年のうちに劇的に変化させ、今まで誰も成さなかった楽器の組み合わせ(ある曲では、わずか数小節のために世界最初のシンセサイザーを導入している!)を試したりと、生涯を通じて「異」なるものを求め続けた作曲家であった。
ともあれ、この「異」的な要素に魅力を感じるのは、あくまで私の感覚であって、これが全てでは決してない。おそらく日本初演となるカマルゴ·グァルニエリの美しい小品に揺られつつ、ここに集った方々がそれぞれの《Encantamento 魅了するもの》を見出して頂ければ幸いである。
<参考>第二次世界大戦以前生まれのブラジルの主要なクラシック音楽作曲家たち
カルロス・ゴメス Carlos Gomes(1836-1896)
レオポルド・ミゲス Leopoldo Miguez(1850-1902)
エンヒッケ・オズヴァウジ Henrique Oswald(1852-1931)
エルネスト・ナザレ Ernesto Nazareth(1863-1934)
アウベルト・ネポムセノ Alberto Nepomuceno(1864-1920)
アレシャンドレ・レヴィ Alexandre Levy(1864-1892)
フランシスコ・ブラガ Francisco Braga(1868-1945)
ホメロ・ジ・サ・バヘット Homero de Sá Barreto (1884-1924)
グラウコ・ヴェラスケス Glauco Velásquez(1884-1914)
エイトール・ヴィラ=ロボス Heitor Villa-Lobos(1887-1959)
ロレンソ・フェルナンデス Lorenzo Fernández(1897-1948)
フランシスコ・ミニョーネ Francisco Mignone(1897-1986)
ジョアン・ジ・ソウザ・リマ João de Souza Lima(1898-1982)
ハダメス・ニャタリ Radamés Gnattali(1906-1988)
カマルゴ・グァルニエリ Camargo Guarnieri(1907-1993)
セーザル・ゲーハ=ペイシ César Guerra-Peixe(1914-1993)
ハンス・ヨアヒム・ケルロイター Hans-Jochim Koellreutter(1915-2005)
クラウジオ・サントロ Claudio Santoro(1919-1989)
ジウベルト・メンジス Gilberto Mendes(1922-2016)
カルロス・ジョビン Carlos Jobim(1927-1994)
オズヴァウド・ラセルダ Osvald Lacerda(1927-2011)
エジノ・クリーゲル Edino Krieger(1928-2022)
マルロス・ノブレ Marlos Nobre(1939-)
リンデンベルグ・カルドーソ Lindembergue Cardoso(1939-1989)
ギレルメ・バウエル Guillermo Bauer(1940-)
アウメイダ・プラド Almeida Prado(1943-2010)
ここに挙げた作曲家はほんの一部に過ぎないが、第二次世界大戦以前生まれの作曲家だけに絞っても、ブラジルという国にはこれだけの名だたる作曲家たちが生まれているのである。
【資料:モザルト・カマルゴ・グァルニエリ -南北アメリカで最も偉大なる音楽家-】
執筆:木許裕介
(Naxos Japan CD解説に寄稿したものをベースに編集)
カマルゴ・グァルニエリは1907年にサンパウロ州のティエテ市で生まれ、1993年に85歳で没した指揮者/作曲家である。グァルニエリと同世代の時代の日本の作曲家では、1906年生まれの大澤寿人、1909年生まれの貴志康一などを挙げられよう。グァルニエリは7つの交響曲、さまざまな楽器のための協奏曲やショーロ、ピアノ曲集「ポンテイオ」をはじめとするピアノ独奏曲、室内楽、カンタータ、オペラ、200以上の歌曲など、生涯に合計600曲を超える作品と14000通にも及ぶ書簡を残した。また、オズワルド・ラセルダなど今日活躍するブラジルの作曲家の多くを育てた教育者・知識人でもある。
ヴィラ=ロボスより20年ほど歳下のこの作曲家もまた、ブラジルのクラシック音楽の創出のために人生を賭けた作曲家であった。ヴィラ=ロボスと同様に、音楽の専門教育を受けることなく、両親より楽器を学ぶところから作曲家の道に進んでいった。
彼の父方はシチリア島の生まれであって、カマルゴの父、ミゲル・グァルニエリが1885年にブラジルに移住し、ジェシア・カマルゴと結婚したことから、グァルニエリ家はブラジルに根付くことになる。ミゲル・グァルニエリはオペラを愛し、趣味としてフルートとヴァイオリンを奏する理髪師。ジェシア・カマルゴはピアノを愛奏した。両親ともに音楽を好んだゆえに、カマルゴ・グァルニエリは洗礼名として「Mozart モザルト」の名前を与えられたという。(兄弟はベッリーニやロッシーニ、ヴェルディの洗礼名を与えられている)
父ミゲルは、カマルゴに音楽を勉強するように薦め、カマルゴは母親からピアノを教わって弾くようになる。11歳で初めての作品としてピアノ曲「芸術家の夢」を作曲。15歳でサンパウロに引っ越したのち、1924年頃からはエルナニ・ブラガとアントニオ・ジ・サ・ぺレイラという二人のピアニストにレッスンを受けるようになる。そして1922年の「近代芸術週間」以降、作曲にも本格的に取り組むようになる。しかし、音楽理論やソルフェージュ、和声や対位法、管弦楽法などを学ぶことができるような音楽院の学生になることはなく、両親からの手ほどき以降は、プライベートレッスンと実地訓練によって技術を磨いていった。床屋であった父親の助手として働きつつ、ヴィラ=ロボスがチェロをあちこちで演奏していたのと同様に、グァルニエリもまた、映画館やカフェやナイトクラブなどでピアノを即興演奏することで生計を立てながら、音楽的素養を形成していったのである。
「作曲家になろうとは微塵も思わずに、ある時はピアノのために、ある時は歌とピアノのために、絶えず曲を書き、そうやって、その楽器を使って日々の糧を得ることに生涯を費やしていました」
後年、グァルニエリは当時を振り返ってこのように語っている。そもそも作曲家になるつもりはなく、サロンのピアニストを生業としていたグァルニエリが作曲家を目指すようになるうえでの決定的な転機は、1926年と1928年の出会いにあった。1926年、グァルニエリはランベルト・バルディという指揮者が指揮する演奏会に足を運ぶのだが、その演奏に感動してバルディの楽屋まで押しかけ、弟子入りを志願したという。(バルディはブラジルに移住してきた外国人指揮者であり、同時代の作品を積極的に取り上げ、「伝説的」と言われるほどに綿密なリハーサルをすることで知られた名指揮者であった)
バルディはグァルニエリに対位法を教え、彼が書いた作品についてもたびたびアドバイスを送るなど、良き師弟関係を築いたようだ。しかし1931年になると、バルディはブラジルを離れてウルグアイのモンテビデオに移住することとなり、グァルニエリの指導を継続することができなくなる。ピアノの師であったブラガとぺレイラもまた、1930年代になってリオデジャネイロに転居してしまい、グァルニエリとの関係が疎遠になってしまった。
もう一つの決定的な出会いは、1928年3月、ブラジル民族音楽運動の父と呼ばれるマリオ・ジ・アンドラージとの邂逅である。グァルニエリはアンドラージに自身の作品を見せたところ、高い評価を受け、ブラジルの国民音楽の創出の担い手として大いに期待を寄せられることになる。アンドラージは「ブラジル音楽についてのエッセイ」においてブラジルの伝統やナショナリティを含んだ音楽のあり方を提唱していたが、その先駆者と看做していたヴィラ=ロボスが、パリに渡ってからはブラジルの野蛮でエキゾチックなイメージを殊更に強調してその地位を築いていることに批判を強めており、自らの理想を真に実現する存在としてカマルゴ・グァルニエリ(と、フランシスコ・ミニョーネ)を見出したのである。
グァルニエリ自身、「私はアンドラージ大学に通っていた」と言っているように、バルディが技術的な師であるとすれば、アンドラージは精神的な師であった。定期的に会合を持って美学、文学、歴史、哲学など幅広い知識を教わる一方で、アンドラージは良き対話者であり、グァルニエリの作品の最も率直な批評家でもあった。グァルニエリは後年このように回想している。「(アンドラージからは)書物への愛、物事を本当に知っている人への尊敬、自分自身への正直さ、素直さ、忠誠心を学びました」「これが私の人生の教訓であり、マリオ・ジ・アンドラージはその最良の模範でした」。なお、「モザルト」に代わり、母方の名前でありサンパウロの伝統的な名前である「カマルゴ」を芸名として採用することを提案したのもアンドラージであった。
もちろん、アンドラージの考えすべてにグァルニエリが従ったのではない。両者の考え方はしばしば相違していて、たとえばストラヴィンスキーの作品をグァルニエリは評価するがアンドラージは評価しなかったし、グァルニエリが1933年に書いた「ヴァイオリン・ソナタ第2番」は無調的な作風であったゆえに、ブラジルの国民的な音楽の創出という観点に合致しないとしてアンドラージはこれを厳しく批判したという。グァルニエリは、民族主義的要素を強く押し出した「ブラジル風舞曲」(1928年)を残す一方で、それとはあまり離れていない時期、たとば1932年から1934年には、無調的なものも手掛けていたのである。
ともあれ、このアンドラージとの出会いが、グァルニエリの人生をサロンの即興ピアニストからプロフェッショナルの作曲家へと導くことになる。1928年から彼は自分の作品目録を作り始めると同時に、「私が1920年から1928年に書いたものはすべて、いかなる状況においても、いかなる理由の下でも、印刷および公開されるべきではなく、批判的かつ比較研究にのみ役立つべきです。」として、1928年までの作品を<禁じられた作品 obra de difusão interdita>として封印した。そして1928年以降の彼は、ブラジルのクラシック音楽言語の創出ということに向き合いながら、交響的な作品を書きうる作曲家を目指しはじめる。結果として1930年代のブラジルにおいては、それぞれにアプローチは違えども、ヴィラ=ロボス、カマルゴ・グァルニエリ、フランシスコ・ミニョーネ、ロレンツォ・フェルナンデスらを通して、国民的な音楽というものが創出されてゆくことになる。
1931年からグァルニエリを応援し続けていた音楽学者ルイズ・エイトールはこう語っている。「カマルゴ・グアルニエリは、音楽から生まれ、音楽のために生きる完全な音楽家であり、その作品は、ブラジルの現代音楽史の中で最も独創的かつ最も強い問題意識を示すものである。」
ここで述べられているように、グァルニエリの抱いた「問題意識」であり、グァルニエリにとっての課題とも言うべきものは「形式」にあった。最終的には50曲にも及ぶピアノ曲集「ポンテイオ」をはじめ、独奏楽器の小品を手掛ければ、かつての即興演奏で磨いた技術が光った。しかし、ある程度の長さを持ったオーケストラのためのオリジナル作品となると、1940年までに作曲されたシンフォニックな作品は1930年作曲の「Curuçá クルサ」(1楽章形式で12分程度。初演はヴィラ=ロボス指揮)や1931年作曲の「ピアノ協奏曲第1番」(3楽章形式で18分程度。初演はグァルニエリ指揮)など、数えるほどしか完成させていない。グァルニエリがクラシック音楽の作曲家として世界に認められる上では、オーケストラを対象として、伝統的な形式の中である程度の長さを持った作品を書く(その最たるものが「交響曲」である)ということが必要であった。そしてそのためには、1931年に別れてしまった技術の師・バルディに次いで、誰か作曲の師について、さまざまな理論を学ぶことが急務であった。つまりはブラジルではなく、クラシック音楽の本流たるドイツかイタリアかフランスのいずれかに渡って作曲を師事することが求められていたのである。
ヴィラ=ロボスがピアニストのアルトゥール・ルービンシュタインによって見出されてパリに渡るきっかけを得たように、グァルニエリもまた、ピアニストのアルフレッド・コルトーによって見出され、パリへの切符を手にすることになる。コルトーはウルグアイを演奏旅行で訪れた際に、グァルニエリのかつての師であるランベルト・バルディに会い、このあとブラジルに行くと伝えたところ、バルディがグァルニエリの存在を伝えたようだ。サンパウロを訪れたコルトーはグァルニエリの人間性と「ポンテイオ」などの作品に心動かされ、パリに留学できるようにサンパウロ州知事に推薦状をしたためる。コルトーの手紙が役に立ったかどうかは定かではないものの、グァルニエリは1937年に奨学金付きの留学に応募し通過。同年、バイーア州を訪れてブラジル北東部の伝統音楽を研究したり、室内アンサンブル作品「トレメンベーの花」を作曲したりと着実に準備を進めながら、1938年6月から1939年11月までパリに滞在することになる。1920年代にヴィラ=ロボスが、1940年代にクラウジオ・サントロが成すように、グァルニエリもまた、パリにおいて様々な芸術家たちと交流を持ち、当時の最先端の作品や演奏に触れることになる。
しかしグァルニエリにとっては、バルディとの別れ以来学ぶことができなくなっていた作曲の技術を学ぶことが何よりも必要であった。そのためにシャルル・ケクラン(マスネとフォーレの弟子にあたる)のクラスに入って和声やフーガを学び、sy(パリ・オペラ・コミック座の首席指揮者)に指揮を学んだ。また、ダリウス・ミヨーやアーロン・コープランドと出会い、ナディア・ブーランジェにもその作品が知られるようになった。とくにコープランドとの出会いは大きく、コープランドは1941年にブーランジェに向けて「最も優れた才能の持ち主の一人」としてグァルニエリを高く評価する手紙を残すほどで、その後アメリカでグァルニエリが活動するうえでの窓口のような役割を果たすことになった。
しかし、この時のパリ滞在は、資金難と第二次世界大戦の勃発により、グァルニエリが期待していたほどの学びを得ることはできなかった。「庭はほとんどセメントで固められた塹壕になっている。(…)5日前、パリの雰囲気は耐えがたくなった。みんな逃げている。」
このような状態で、グァルニエリは予定より早い帰国を余儀なくされることになった。すでにヴァルガス政権に深く食い込んでいたヴィラ=ロボスや教授職のポストを持っていたフランシスコ・ミニョーネと異なり、何ら安定した仕事を持たないままヴァルガス政権下のブラジルに戻らざるを得ないことになったグァルニエリは、帰国直後はかなり苦しい日々を過ごしたようだ。また、1939年にはケルロイターの指導下で前衛音楽グループMusica Vivaが結成されて、十二音音楽やセリー音楽を進める流れも生まれつつあったので、帰国してすぐに政治的・文化的な混乱の渦に巻き込まれたようなものであった。
しかし1942年、「ヴァイオリン協奏曲第1番」がパン・アメリカンユニオンの賞に選ばれることとなり、コープランドの手引きもあって42年10月1日よりアメリカを訪れる。1941年12月の真珠湾攻撃を受けて、アメリカ本土も開戦状態にある中での訪米であったため、受け入れには相当な困難があったらしい。しかし結果として、ここで築いたアメリカおよびコープランドとの縁はその後のグァルニエリの人生に大きな影響を与えた。グァルニエリは指揮者として、ブラジルにおける現代アメリカ音楽の紹介者になってゆくのである。訪米後、コープランドは、指揮者のセルゲイ・クーゼヴィツキーを紹介。前衛の庇護者として知られ、プロコフィエフやスクリャービン、ストラヴィンスキーをアメリカで積極的に紹介していたクーゼヴィツキーは、グァルニエリの作品にも強い興味を持ったようである。この縁からボストン交響楽団でグァルニエリの「協奏的序曲」を作曲者自身が指揮する機会を得た。さらにニューヨーク近代美術館ではグァルニエリの作品だけのコンサートが催され、「チェロ・ソナタ第2番」などが演奏された。この時ピアノを弾いたのは24歳のレナード・バーンスタインであり、その後バーンスタインもまた、アメリカにラテン・アメリカ音楽を紹介する主要な役割を担うことになるのである。
このアメリカ滞在中から、悲願であった「交響曲第1番」を書き始める。1943年4月にブラジルに帰国し、1944年に交響曲第1番(クーゼヴィツキーに献呈)を完成させると、この作品がサンパウロにおいてLuiz Alberto Penteado Rezende 賞を受賞。ミニョーネに「ブラジルでは、今日に至るまで、この作品ほど論理や形式的発展が完全に実現された作品を書いた者はない。そして、おそらく海外でも、芸術的完成度において匹敵するものは無いだろう。」と絶賛され、アンドラージに「ブラジルにおける過去最高のポリフォニー作曲家」と評された。(なお、アンドラージは1945年に他界している) ついで1946年、交響曲第2番「ウィラプルー」がアメリカ交響曲コンクールで第2位のレイチョルド賞を受賞。交響曲第2番は同名の交響詩を書いたヴィラ=ロボスに献呈されている。
ヴィラ=ロボスが野性的な天才のイメージとともにその卓越した管弦楽法によって「ブラジルのレスピーギ」のような位置付けにあったとすれば、フランシスコ・ミニョーネはその美しい旋律ラインによって「ブラジルのプッチーニ」であった。一方でカマルゴ・グァルニエリは、民衆に訴えかけるような作風ではなく、形式をはじめとするさまざまな論理との格闘を深めていたこともあって、当時は掴みどころの無い作曲家であると認識されていたのかもしれない。しかし彼は、単に民族音楽の旋律の模倣に陥ることなく、より深く国民音楽的でありながら、より普遍的で古典的であることができるかということを問い続けていた。そしてそれは北米のモダニズム音楽が抱えていた問いと響き合うものがあり、グァルニエリの音楽は北米においていち早く受け入れられることになったのである。結果としてグァルニエリの作品を広めたのは、ブラジル以外では北米の音楽家やオーケストラであり、アーロン・コープランド、レナード・バーンスタイン、レオポルド・ストコフスキー、シカゴ交響楽団、ボストン交響楽団、ニューヨーク・フィルハーモニックなどによって彼の作品が演奏され、その名を国際的に轟かせていくことになる。
交響曲を手掛け、世界的な作曲家として認められつつあったグァルニエリは、1950年代からは作曲家として、指揮者として、教師として、世界各地を飛び回るようになる。教師としてはオズヴァルド・ラセルダ、アルメイダ・プラド、グエッラ・ペイシェ、クラウジオ・サントロなどを教えた。また、この時期には恩師・バルディに連絡を取ってモンテビデオで指揮したことも記録に残っている。モンテビデオに移り住んでいたドイツの音楽学者、クルト・ランゲと築いたパートナーシップも、グァルニエリの作品を出版するうえで極めて重要な役割を果たすことになった。
1950年、グァルニエリは「ブラジルの音楽家と批評家への公開状」を出して、十二音技法やケルロイターの手法はブラジルの音楽的アイデンティティを脅かすものであるとして痛烈な批判を展開。(ただし近年の研究で、この公開状はグァルニエリによるものではなく、グァルニエリの弟によるものであった可能性が挙げられている。)折しも1948年には、クラウジオ・サントロが「第2回 作曲家と音楽評論家の国際会議」(通称プラハ会議)に出席し、十二音技法の限界に触れ、十二音技法を手放すという宣言をしたばかりであったこともあり、この公開状はブラジルの音楽シーンに大論争を巻き起こすことになる。
1951年には「ヴァイオリンとオーケストラのためのショーロ」を作曲、ついで1952年にはサンパウロ市政400周年を祝して交響曲第3番を作曲。この作品は1954年のサンパウロ市政400周年コンクールで第1位に輝き、恩師であるランベルト・バルディに献呈された。(なお、サンパウロ創立400周年の記念式典のために同時期に作曲された作品がヴィラ=ロボスの交響曲第10番「アメリンディア」である)
以降、1961年までに4つのショーロ、1つの協奏曲、3つの組曲、1つの交響曲を作曲しながら、1956年には教育文化省の音楽芸術補佐に就任。また1959年にヴィラ=ロボスが没すると、その後を継いでブラジル音楽アカデミーの会長に就任。さらに同年、サンパウロ州政府より名誉市民賞を与えられた。
1960年代から70年代にかけては、サンパウロ演劇音楽院教授、サントス音楽院教授、ミナスジェライス州ウベルランジア大学教授などを務め、1975年には新しく創立されたサンパウロ大学交響楽団の芸術監督・指揮者に就任。この間、交響曲第4番(1964)や「ピアノと室内オーケストラのためのセレスタ」(1965)「ヴィラ=ロボスへのオマージュ」(1966)「ヴィオラとオーケストラのためのショーロ」(1975)、交響曲第5番(1977)などを生み出した。
1981年にはソビエト政府に招かれモスクワ現代音楽祭に参加。また、ポルトガルのポヴォア・ド・ヴァジム国際音楽祭にも招かれる。クリーヴランドで開かれたロベルト・カサドゥシュ・ピアノ・コンクールの審査員も務めている。サンパウロ市立劇場70周年を記念してサンパウロ市文化局から依頼された交響曲第6番を1981年に完成させ、1985年にはマックス・ベッファー家の依頼で、最後の交響曲となる交響曲第7番を作曲。次いで、最後のピアノ協奏曲となるピアノ協奏曲第6番「サラティ」を1987年に作曲。1990年に咽頭癌と診断されるも、1991年に「ファゴットと室内オーケストラのためのショーロ」を完成させる。1992年、「アメリカ大陸で最も偉大な作曲家」として米州機構よりガブリエラ・ミストラル賞を受賞。そして1993年1月13日、サンパウロ大学病院で永眠した。